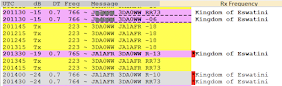<11/7>
変更申請は前回同様、電子申請システムを利用。今回の変更は、現在ハイパワー免許を受けている7/14/21/28/50MHzに加え、3.5/3.8/10/18/24MHzを1kWとする内容。1.9MHzは3.5MHz用のInverted-Vにローディングコイルを付加する場合、耐圧の課題があり、また例え免許を下ろしてもこの住宅環境下でハイパワー運用は現実的ではないと判断し対象外とした。
設備構成はアンテナを除いて3年前の申請当時と変わらないため、添付資料の大半は、前回使用したものを一部修正するだけで事足りた。
申請に用いた文書は以下のとおり;
1.変更申請書 ※電子申請システムで作成
2.無線局事項書及び工事設計書 ※電子申請システムで作成
3.添付資料
(1)送信機系統図
(2)他の無線局の設置状況を示す図面
(3)設置場所でのTV・ラジオ放送の受信状況一覧表
(4)アンテナの道路越境に係る確認書
(5)電波防御指針に基づく基準値に適合していることの証明書
①電界強度計算表(南側道路/最短近接住宅/南西住宅)
②アンテナを中心とした平面図(広域図/詳細図)
③アンテナを中心とした立面図(南北面/東西面)
④アンテナの垂直面指向特性図(俯角減衰量計算用)
⑤アンテナの利得・エレメント寸法に関する資料
⑥給電線損失(フィルター挿入損失含む)に関する資料
添付資料は合計で15種類。全てExcelシート(A4/縦)で作成し、システム送信時のファイル容量制限を考慮して2ファイルに分けて添付した。
③アンテナを中心とした立面図(南北面/東西面)
④アンテナの垂直面指向特性図(俯角減衰量計算用)
⑤アンテナの利得・エレメント寸法に関する資料
⑥給電線損失(フィルター挿入損失含む)に関する資料
添付資料は合計で15種類。全てExcelシート(A4/縦)で作成し、システム送信時のファイル容量制限を考慮して2ファイルに分けて添付した。
以下、新規作成したアンテナに関する資料。
●電界強度計算表への記載は、今回の変更申請分だけではなく、既にハイパワー免許を受けている周波数も併記すること
●アンテナを中心とした平面図(詳細図)に電界強度の計算を行なった3地点をプロットすること
●3.5MHzアンテナに係る空中線地上距離(平面)および地上高(立面)の測定は、給電点(バラン位置)ではなく、エレメント(ワイヤー)が地上および隣家に最も近接するポイントから測ること
11/28に上記を補正した上で添付ファイル(全て)を再送。
<12/8>
補正申請から10日ほどで「審査終了」のメールが来着。前回のハイパワー変更申請では審査終了時にメールは来ておらず(毎日ステータスが変わるのをチェック)不可解に思いつつメールを読むと、審査終了後の免許状交付に関する案内であった。
補正申請から10日ほどで「審査終了」のメールが来着。前回のハイパワー変更申請では審査終了時にメールは来ておらず(毎日ステータスが変わるのをチェック)不可解に思いつつメールを読むと、審査終了後の免許状交付に関する案内であった。
もしかして設備構成が何ら変わらず周波数の追加のみであれば、これで免許されるのか..と考えたが(検査事業者からも同様のコメントあり)翌日、関東総通局に電話で確認。
「このようなメールが届いたが、このまま免許されるのですか」と尋ねると「その内容ならば多分そうであろう・・」と曖昧な返答。理由が解せないので電子申請番号を伝えて調べてもらうと「確認したところ変更検査が必要でした・・」との事。
メールは電子申請システムからの自動配信のようであり、ハイパワー申請であっても「審査終了」のフラグが立つと一般の変更申請と同じ内容のメールが飛ぶらしい。真偽のほどは定かではないが..
翌日に120円切手を貼付した返信用封筒(角形2号)を同封して関東総通局に「無線局変更許可書」等の書類送付を依頼。
<12/14>
関東総通局から以下の書面が来着。
関東総通局から以下の書面が来着。
・無線局変更許可書
・アマチュア局変更申請者(200W超)に対する指示文書
・電波障害調査等の提出について
・アマチュア局検査申込書(様式1)
・アマチュア局検査事前点検表(様式2)
・電波障害調査依頼書/回答書(様式3)
無線局変更許可書の日付は12/8。電子申請開始から1ヶ月で指定変更工事の許可を得ることができた。
指示文書を含め様式類は、3年前と同じ内容であったが、唯一、国の検査を希望する場合「コロナ禍の影響で(検査までに)半年程度時間を要する場合がある」と朱書きされており、検査は前回同様「登録検査等事業者制度」に基づき検査事業者に依頼することにした。
翌日(12/15)関東総通局に「試験電波発射届」を郵送。試験開始日は12/18として、年内に電波障害調査を終わらせる段取りとした。